【日程変更】ナガサキ・ユース代表団によるオンラインイベント(5月24日)のお知らせ
延期していましたナガサキ・ユース代表団第8期生によるオンラインイベント「人類みなヒバクシャになり得る、人類みなヒバクシャを生み得る」を5月24日に開催いたします。[英文のお知らせへ]
| 日 時: | 5月24日(日)午後10時~11時(日本時間) |
| 形 式: | オンライン(Zoom) |
| 言 語: | 英語 |
テーマ: | 人類みなヒバクシャになり得る、人類みなヒバクシャを生み得る |
| 主 催: | ナガサキ・ユース代表団第8期生 |
| 後 援: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会 (PCU-NC) |
≪参加方法≫ 新規に参加をご希望の方は こちら から事前登録をお願いします。登録後、参加用のURL をご案内いたします。前回登録していただいた方の再登録は不要です。
このイベントで行うプレゼンテーションは、本来今年の4月~5月に米国・ニューヨークで開催される予定であった核不拡散条約(NPT)再検討会議のサイドイベントの一環として発表する予定だったものです。新型コロナウィルスの感染拡大により会議自体が延期となったため、一部内容を修正の上、オンラインで発表することとしました。
現在地球上にまだ14,000発近い 核弾頭 が存在する中で、若い世代が長崎・広島の被爆の経験と被爆者の言葉から何を学び、また、その悲劇を繰り返さないために自分たちがどのような姿勢で核に向き合うべきなのか、真剣に考えてきた過程を報告します。
このプレゼンテーションを通して、一人でも多くの方が「核兵器の問題は自分の問題」であることに気付いていただければと期待しております。
ナガサキ・ユース代表団とは?
ナガサキ・ユース代表団 は、2012年に長崎県、長崎市、長崎大学の三者が核兵器廃絶に取り組むために設立した 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)の人材育成プログラムです。
【お問い合せ】nagasaki.youth8th@gmail.com
5月17日実施予定のナガサキ・ユース代表団によるオンラインプレゼンテーションの延期について
5月17日に実施を予定していましたナガサキ・ユース代表団第8期生によるオンラインプレゼンテーションについては、オンライン(Zoom)システムの不具合により実施することが出来ず、延期することといたしました。
急な予定変更で大変申し訳ございません。
延期後の実施日時等が決まりましたら、改めてご案内いたしますので、引き続き、よろしくお願いいたします。
【本件に関するお問い合せ先】
核兵器廃絶長崎連絡協議会
Email: pcu_nc@ml.nagasaki-u.ac.jp
ナガサキ・ユース代表団によるオンラインイベント(5月17日)のお知らせ
ナガサキ・ユース代表団第8期生が、「人類みなヒバクシャになり得る、人類みなヒバクシャを生み得る」と題して、英語によるオンラインイベントを実施します。[英文のお知らせへ]
| 日 時: | 5月17日(日)午後10時~11時(日本時間) |
| 形 式: | オンライン(Zoom) |
テーマ: | 人類みなヒバクシャになり得る、人類みなヒバクシャを生み得る |
| 主 催: | ナガサキ・ユース代表団第8期生 |
| 後 援: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会 (PCU-NC) |
≪参加方法≫ こちら から事前登録をお願いします。登録後、参加用のURL をご案内いたします。
このイベントで行うプレゼンテーションは、本来今年の4月~5月に米国・ニューヨークで開催される予定であった核不拡散条約(NPT)再検討会議のサイドイベントの一環として発表する予定だったものです。新型コロナウィルスの感染拡大により会議自体が延期となったため、一部内容を修正の上、オンラインで発表することとしました。
現在地球上にまだ14,000発近い核弾頭が存在する中で、若い世代が長崎・広島の被爆の経験と被爆者の言葉から何を学び、また、その悲劇を繰り返さないために自分たちがどのような姿勢で核に向き合うべきなのか、真剣に考えてきた過程を報告します。
このプレゼンテーションを通して、一人でも多くの方が「核兵器の問題は自分の問題」であることに気付いていただければと期待しております。
ナガサキ・ユース代表団とは?
ナガサキ・ユース代表団 は、2012年に長崎県、長崎市、長崎大学の三者が核兵器廃絶に取り組むために設立した 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)の人材育成プログラムです。
【お問い合せ】
Email: nagasaki.youth8th@gmail.com
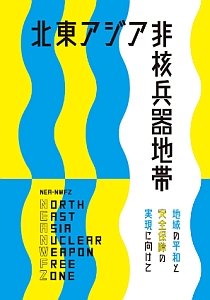 核兵器のない、より平和で安全な北東アジアを実現する道として、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)が提唱している「北東アジア非核兵器地帯(NEA-NWFZ)と包括的アプローチ」について、コンパクトに解説しています。
核兵器のない、より平和で安全な北東アジアを実現する道として、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)が提唱している「北東アジア非核兵器地帯(NEA-NWFZ)と包括的アプローチ」について、コンパクトに解説しています。
こちら からリーフレット(2020年eBook版)をご覧いただけます。ページの右端をクリックするとページが進みます。ページの左端をクリックするとページが戻ります。他に、PDF版 【閲覧用】【印刷三折用】 もあります。
2020年4月27日から5月22日まで開催される予定であった、核不拡散条約(NPT)再検討会議が、新型コロナウィルス感染症拡大をうけて最長来年4月までの延期が決定されました。RECNAとしては、延期を踏まえたうえで、NPT発効50年、被爆75年という節目の年を迎えたNPT体制について、現状の課題と展望をわかりやすくまとめました。
全文は こちら です。是非ご覧ください。
RECNAニューズレター Vol.8 No.2 (2020年3月31日発行)
PSNAワーキングペーパー “The 2018-2019 Summitry Process and Prospects for Denuclearization of the korean Peninsula” (PSNA-WP-12) が公開されました。日本語のタイトル及び要旨は次のとおりです。
2018-19首脳会談プロセスと朝鮮半島非核化プロセスの展望
(PSNA-WP-12)
(要旨)
大統領選挙に関心がいっている米国の状況や関係諸国の対話が進んでいないことを考えれば、朝鮮半島の非核化はここ数か月は進展しないだろう。このような状況下でのベストな選択は「これ以上悪化させないこと」であり、今後の非核化プロセスの進展に障害を作らないことだ。今後、このプロセスを進展させる最善のアプローチは、多国間交渉に持ち込むことだ。「P3⁺3」(3核兵器国と北朝鮮、韓国、日本)の6か国で交渉する形をとるのが一番だ。その際、日本がこのプロセスでより積極的な役割を果たすことが期待される。
英語版のみとなりますが、全文は こちら からご覧いただけます。
PSNAワーキングペーパー “China’s Dilemmas over Stalled North Korean Denuclearization Talks” (PSNA-WP-11) が公開されました。日本語のタイトル及び要旨は次のとおりです。
停滞する北朝鮮非核化プロセスにおける中国のジレンマ
(PSNA-WP-11)
(要旨)
停滞する北朝鮮非核化プロセスを進めるうえで、中国の役割は大きい。しかし、中国の真意を疑う見方もある。中国には、長期的に非核化を進めたい目的と、短期的には地域の地政学的バランスを守りたいというジレンマがある。そのジレンマにもかかわらず、本論文は、中国がとる短期的施策と、関係国と協力して非核化を進める長期的施策を提言する。
英語版のみとなりますが、全文は こちら からご覧いただけます。




















