《東京》公開国際シンポジウム
「北東アジア非核兵器地帯へ―地域安全保障のための包括的アプローチ」
“Toward a NEA-NWFZ―A Comprehensive Approach to the Regional Security”
| 日時: | 2012年12月10日(月) 18:00-20:00 |
| 場所: | 明治学院大学白金校舎・本館10階大会議場 |
| 共催: | 核軍縮・不拡散議員連盟(PNND)・日本 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC) 明治学院大学国際平和研究所(PRIME) ノーチラス研究所 長崎大学 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |
 |
 |
 |
| 進行の梅林宏道RECNAセンター長 | オープン・ソサエティ財団上級顧問の モートン・H・ハルペリン博士 |
ノーチラス研究所所長のピーター・ヘイズ博士 |
| 開会挨拶: | 稲見 哲男(前衆議院議員) 調 漸(核兵器廃絶長崎連絡協議会会長) |
|
| 進行: | 梅林 宏道(長崎大学核兵器廃絶研究センター長) | |
| 基調講演: | モートン・H・ハルペリン(オープン・ソサエティ財団上級顧問) |
|
| パネル討論: |
ピーター・ヘイズ(ノーチラス研究所所長) |
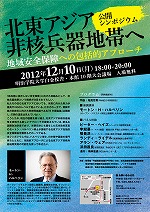 チラシ |
《長崎》公開国際シンポジウム
「北東アジア非核兵器地帯の実現へ―新しいアプローチの可能性」
“Towards a NEA-NWFZ―Time for a New Approach”
| 日時: | 2012年12月8日(土) 15:00-17:00 |
| 場所: | 長崎大学文教キャンパス・新棟4階ホール |
| 共催: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会 長崎大学 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |
 |
 |
 |
| オープン・ソサエティ財団上級顧問 モートン・H・ハルペリン博士 |
ノーチラス研究所所長 ピーター・ヘイズ博士 |
パネル討論の様子 |
| 主催者挨拶: | 田上 富久 (長崎市長) 片峰 茂 (長崎大学長) |
|
| 基調講演: | 梅林 宏道 (長崎大学核兵器廃絶研究センター長) 「新しいアプローチの必要性」 モートン・H・ハルペリン (オープン・ソサエティ財団上級顧問) 「包括的協定の提案」 |
|
|
パネル討論: 閉会挨拶: |
【モデレーター】 |
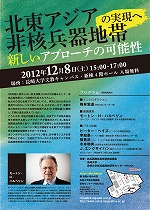 チラシ |
「英語で伝える<ナガサキ>と<核兵器のいま>」
| 日時: | 2012年11月21日(水) 17:30-20:00 |
| 場所: | RECNA 1階会議室 |
| 講師: | スティーブン・リーパーさん (広島平和文化センター理事長) |
| 共催: |
核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC) |
 |
 |
 |
| スティーブン・リーパーさん | 勉強会の様子 | 積極的に発言をする学生 |
米国出身で反核平和運動に長く携わってきたスティーブン・リーパーさんを講師に迎え、生きた英語で長崎の原爆や現在の核兵器をめぐる情勢について学びました。
一人一人が考える力を身につけ、それを世界の人々と議論してゆく英語力のアップを目指して、高校生・大学生約15名が参加しました。
長崎発の核軍縮に関する英文ニュース「Dispatches from Nagasaki」の第3号を掲載しました。(日本語対訳付)
>>詳しくはこちら
第1回 核兵器廃絶市民講座 「核兵器と核軍縮の現状は?」
| 日時: | 2012年11月27日(火) 18:00-20:00 |
| 場所: | 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 交流ラウンジ |
| 講師: | 梅林 宏道 (RECNAセンター長) |
| 主催: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC) |
| 共催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |
 |
 |
| 講義をする梅林宏道RECNAセンター長 | 会場の様子 |
平成24年度核兵器廃絶市民講座の第1回が11月27日(火)に国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 交流ラウンジにて行われました。
初回の講師はRECNAセンター長の梅林宏道先生が務め、『核兵器と核軍縮の現状は?』と題して、核兵器保有の現状や核兵器なき世界への手掛かりについて講義しました。
講座には約50名の市民が集まり、核兵器廃絶に向けた世界の動きを学びました。
米国が3か国イニシャチブに反対
ここでは、米国をはじめロシア、フランスなど核兵器国が一般討論(10月8日~16日)と核兵器に関するテーマ別討論(10月17日~22日)においてどのような姿勢を示したかを中心に報告し、「核兵器のない世界」に向けたこれらの国々の対処の姿勢を論評する。
大統領選挙直前の時期にあたる米国の姿勢は、一貫して後ろ向きとの印象を禁じ得ない。10月10日の一般討論に登壇したローズ・ガテマラー国務次官補(英文)も10月17日のテーマ別討論に登場したローラ・ケネディ軍縮大使(英文)も、オバマ大統領のプラハ演説を引き合いに出して、「核兵器のない世界」を目指すために米国は活発に活動していると強調した。そして、米ロのSTARTが順調に実行されていると述べ、ステップ・バイ・ステップ(一歩一歩)の方法でしか「核兵器のない世界」に近づく方法はないと従来の主張を繰り返した。日本政府が同じ主張を自信に満ちた様子で強調する姿を見るたびに、その後ろに、筆者はいつもこのような米国の姿勢を二重写しにしてきた。
米国は、そのようなステップ・バイ・ステップの次の第一歩は兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約、FMCT)であると考えている。そしてFMCT交渉開始がジュネーブ軍縮会議(CD)で行き詰まっている状況を打破するために、CDに代わる道を追求することを辞さないと述べてきた。ガテマラー氏は10日に「米国はいつも革新的であったし今もそうである。軍備管理や不拡散においても例外ではない」と述べた。しかし、10日に、オーストリアが、CDの停滞を破りFMCTを含む核軍縮アジェンダ全体を前進させる意図で「革新的」提案(第1報参照)を行った後に米国が用意した17日の演説は、オーストリア提案に真っ向から反対するものであった。
17日、FMCT交渉のために米国が追求してきたCDへの対案――5核兵器国といくつかの国が議論してきたもの――が、停滞を打ち破る唯一の方法であると主張したのちにケネディ米大使は次のように述べた。
「核兵器のない世界を達成するために代案となる総体的アプローチの要求が出ている。目指すところは同じであるが、根本的なところでこのアプローチに同意できない。軍縮は誰もが知るように困難な仕事である。近道はないしステップ・バイ・ステップ・アプローチの他に実際的な代案はない。一気にすべてを達成しようとするとより現実的な努力がおろそかになる。このような理由で、核軍縮を扱う新しい国連機構を設立しようとする提案を我々は支持しない。このような機構は決して現状より良いものにならない。」
これは、強い内容をもった失望すべき意見表明である。米国の「革新性」は従来の路線の継承を前提とする範囲のものだということを示す結果になった。CDがFMCT追求の唯一の場であるべきであるという意見は、ロシア、中国、フランス、イギリスのすべてが繰り返した。オーストリアら3か国イニシャチブの前に立ちはだかるこの壁に対して、今回の第1委員会がどのような結論を出すのか、注視したい。
P5、核軍縮停滞に反省なく、努力を自賛
米国は、戦略と非戦略、配備と非配備を含むすべての核兵器の次なる削減についてロシアと対話を始めていると述べた。また、米国は新型核弾頭を製造することを禁じているし、新しい任務を核兵器に与えていないことを改めて確認した。しかし、核弾頭の寿命延長計画や弾頭の非核部分の改造で事実上の新型核弾頭の開発や新任務の付与(の可能性)を行っているという専門家が指摘してきたことに対して反論する情報は与えられなかった。
STARTの一方の当事者であるロシアは、STARTに関して米国とは異なる取り上げ方をした。さらなる核兵器削減のための米国との交渉について、きわめて率直に悲観的見解を表明したのである。それは米国のミサイル防衛に関する深刻な懸念に基づくものであり、警告に近い内容である。10月10日、ミハイル・ウリャノフ・ロシア外務省安全保障問題及び軍縮部長は次のように述べた(英文)。
「実際には、(米国との)新しい(核削減)合意はますます幻想になりつつある。グローバルな弾道ミサイル防衛システム(BMD)を開発する一方的な計画を性急に実行しようとすることから生じている構造的な変化によって戦略的安定性が悪影響を受けている。本質的に、これは他人の安全保障を犠牲にして自分の安全保障を確保しようとする試みであり、ヨーロッパと国際的な安全保障という根本的原則に反している。すべての国が、このような措置がもたらす破滅的な結果に気付いているわけではない。しかし、実際のところ遠からず核軍縮の望みが絶たれてしまう傾向が生まれている。さらに、制限もなく、あるいは全体的な国際的文脈や他の国家が抱く正当な関心への考慮もなく、BMDシステムを一方的に配備することは、不可避的に対抗手段を引き起こし、危険な対決の前提やおそらくは新しい軍備競争を生み出すであろう。」
ロシアはMDがある種の現実的な脅威に対して有効であると認めることによって、米国にMDに関する米ロの対話を促し、演説の中で両国に利益となるMDの構築の可能性を呼び掛けた。この呼びかけは新しいものではなく、すでに米国議会によって強く拒否されてきた。今回も事態を改善する役割を果たさないと見るべきであろう。
ロシアの警告に真実味があるだけに、冷戦時代と同じ東西対立の構造を再現させない世界的世論が必要になっている。
中国の演説にも新味がなかった。米ロという国名を掲げることは避けながら、最大の核兵器を保有する国(複数)が核兵器の大幅削減に先頭を切って取り組むべきだと主張するとともに、それによって包括的な核軍縮の条件が生まれると述べた。その先の適切な時期に、国際社会は核兵器禁止条約を結ぶべきであるとも述べた。中国が一貫して強調してきた先行不使用(ノー・ファースト・ユース)政策や、無条件に非核兵器国に対して核兵器の使用や使用の威嚇を行わない(無条件の消極的安全保証)政策をとっていることを強調し、すべての国がこれらを行うことを義務付ける条約を締結すべきであると主張した。確かに中国の核兵器政策は他の核兵器国と比較してユニークであり、一歩前進したものである。しかし、世界的な核軍縮を進めるためにリーダーシップをとるために何をするかという観点からの、新味のある提案が欠けているのは残念である。
フランスもまた自国が軍縮努力を怠っていないことを強調したが、2010年のNPT再検討会議にすでに述べたことを超える内容はなかった。自国の戦略原理を「厳密な十分性の原則、すなわち国際環境に見合った最低の可能なレベルに保有核兵器を維持する」ものだと説明を改めて繰り返した(10月17日、シモン-ミシェル国連大使)(英文)。中国もまた「国家安全保障にとって必要な最低レベルの核兵器能力の維持」という言葉を使うが、中国と比較したとき、先行不使用、無条件の消極的安全保障などの政策表明がない分だけ、フランスの「原理」――国際環境によって変わる「厳密な十分性」の概念――は、極めてあいまいであるとの印象を拭いえない。
イギリスはNPTの核軍縮義務を履行していると胸を張った。しかし、将来の安全保障環境が不透明である以上、「信頼できる効果的な最小の核抑止力を維持する」と従来の立場を繰り返した(10月18日、アダムソン大使)(英文)。英国の核戦力は、現在、潜水艦戦力のみであるが、2010年の「戦略的国防・安全保障見直し」(SDSR)で定めた削減計画――1隻当たり搭載の弾頭数を48から40に削減し、作戦用弾頭数を120以下に減らせ、1隻当たりの核ミサイル8基以下にし(すなわち5発以下の多弾頭ミサイル)とし、貯蔵核弾頭の総数を180以下にする――という目標について、すでに実行に移されており、潜水艦の1隻についてはすでに弾頭数が40以下を達成したと報告した。また、2015年のNPT再検討会議までに作戦弾頭数を120以下を達成すると発表した。これらの情報の一部は新しいものである。
すべての核兵器国が、NPT合意を順守するためのP5の会合を継続していることについて、彼らの誠意の証として言及した。会合が5核兵器国の信頼醸成に役立っていることは確かであろう。もっとも最近の会議は12年9月27日~28日に北京で開かれた専門家会議であった。10月18日の中国の発言(英文)によれば、それは「主要な核に関する専門用語の定義集に関して作業する初めての専門家会合」であったが、「核に関する用語集を作成する作業を、相互理解と意見交換を強めることを目指してスピードアップすることを決定した。」イギリスが述べているように、P5が2010年NPT行動計画によって求められている「標準的報告様式」の提案を行うためには、技術的議論を一層速めなければなるまい。さらに、形式ではなく透明性を確保したうえでの削減のペースについても、建設的な議論が行われるべきであろう。
まえがき
国連総会には6つの委員会があるが、そのなかで第1委員会は総会が扱うべき「軍縮と国際安全保障」に関わるすべての問題を扱う。
2012年の第67国連総会は9月18日に開会した。多くの国の首長が登壇した一般演説を終えたのち、第1委員会(議長:デスラ・ペルカヤ大使、インドネシア)は10月8日に開会した。
このモニターは第1委員会の議論のすべてを追跡するのではなく、核兵器に関わる議論に限定して追跡する。確かに核兵器問題は議論全体の中で重要な部分を占めるが、私たちは、つねに世界の平和と安全保障を実現する国連の役割全体を視野に入れて考える姿勢を失ってはならないであろう。今回の第1委員会をみても、7月の最終的交渉で決裂した武器貿易条約(ATT)の問題や、飢餓や疾病に苦しむ大多数の人々への投資よりも巨額の軍事費への投資が優先される現実に、多くの国が厳しく言及した。さらに、シリアの内戦に象徴される武力衝突が毎日のように一般市民の命を奪い難民を生み出している最中に会議が開かれているという現実感覚を、私たちは持ち続けなければならない。
核兵器問題に限定して考えた場合、今回の第1委員会は、2010年NPT再検討会議で一定の前進を勝ち取ったのち、2011年2月の米ロ戦略兵器削減条約(START)の発効以来、2年近くも「核兵器のない世界」への動きが停滞に陥っている現実を反映している。とりわけ、2012年もジュネーブ軍縮会議(CD)が行き詰まりを解決できなかったという苦い現実を背負って第1委員会は協議を開始した。憂慮する良心的な国々は、責任感と創意をもって会議に臨むはずである。そんな中で日本政府はどうなのか。日本の市民にとってはそれも大きな関心事となる。
第1委員会もまた、10月16日まで「軍縮と国際安全保障」に絞った一般討論を行った。10月17日にはテーマ別討論が始まった。第1報では10月8日~16日の一般討論の中から注目すべき2つの動きについて報告する。
新アジェンダ連合は一歩踏み出すか?
10月8日の一般討論では、新アジェンダ連合(NAC=アイルランド、スウェーデン、メキシコ、ブラジル、ニュージーランド、エジプト、南アフリカの7か国)の発言がまず注目された。今年はスウェーデンがNACを代表して発言した(英文 日本語訳)。NACの現状認識は明確であり一貫している。それは「核不拡散条約(NPT)はすべての側面において、公正に履行されなければならない。しかし、現実には、核不拡散は一定の成功を収めているにもかかわらず、核軍縮の進展は余りにも遅い」というものである。
今回のNAC発言で注目したい点は二つある。いずれも今回が初めての内容ではなく、今年4~5月にウィーンで開催されたNPT再検討準備委員会でも同様なNAC発言があったが、多数決で運営される国連総会に持ち込んだ発言として注目する。
一つはNACが国連事務総長の2008年の提案を念頭に置きながら、核兵器禁止条約に関して次のように触れた部分である。
「核兵器のない世界の達成と維持のための相互に強化しあう国際文書の包括的枠組みを構築するため、すべての国家が努力すべきであることを、NACは今一度訴えます。すべての核兵器の完全廃棄に向けたこのような法的拘束力のある枠組みは、効果的かつ信頼性を持たせるために、明確に定義された評価基準や行程表を含むとともに、強固な検証システムに裏打ちされていなければなりません。」
一つの核兵器禁止条約というイメージではなく諸条約の包括的な枠組みとして提案し、時間枠を含むような条約を明確に提案していることが注目点である。最大の関心事は、この考えがNACの総会決議案に具現するかどうかである。筆者の主観では相当にハードルが高いと考えられる。
もう一つの注目点は、核兵器国と同盟関係にある国に対して要求した次のような件である。
「継続的で強化された透明性も不可欠です。核兵器国を含む軍事同盟に属している国々は、集団的安全保障ドクトリンにおける核兵器の役割を低減、さらには除去するために計画中の諸措置について報告を行うことで、これに寄与することができるでしょう。」
RECNAのNPTブログの第5報でも述べたように、NACのこの主張は、日本を含むNPDI(核軍縮・不拡散イニシャチブ)が提出した透明性に関する作業文書と深く関係している。日米安保条約は集団的安全保障条約ではないが、日米は安保条約における核兵器の役割を減じるための措置をとるべきであり、そのことを報告することによって透明性の向上に寄与することがでる。
オーストリアなど3か国の再挑戦
オーストリア、メキシコ、ノルウェーの3か国は、昨年の国連総会でCDの行き詰まりを打破するために、革新的で創意あふれる総会決議案を提出した。しかし、内容を薄めて採択される道を選択せず、説得に時間をかけるとして決議案を投票に付すことを断念したという経過がある。RECNAのNPTブログ第2報で述べたように、ウィーンで開かれたNPT再検討準備委員会でメキシコは、今回の国連総会で再挑戦する可能性を示唆していた。
期待通り、10月10日の一般討論において、オーストリアは「多国間の核軍縮にダイナミックな力学を取り戻すことを目指して、同志国家とともに決議案を起草することを決意した」と述べた。決議の内容については次のように述べた。
「このイニシャチブの目的は、来年中に3週間までの会期を持つ会議をジュネーブに招集する無期限ワーキング・グループを設置することによって、核軍縮の分野での多国間の実質ある前進をめざすことにある。ワーキング・グループの任務は、「核兵器のない世界」の達成と維持のための多国間交渉を前進させる具体案を作成することにある。結果いかんに偏見をもたず、建設的で実質のある作業をするためのフォーラムになることを目指す。」
この内容だけでは決議案の全貌は分からないが、昨年の決議案と同じではなく、より練られた内容として再提案されるように見受けられる。
10月12日には、ノルウェーも3か国提案に言及し、「核兵器のない世界という私たちの共通の目標を達成するためには、新しいアイデアとアプローチを発展させることが切実に求められている。オーストリア、ノルウェー、メキシコが提案する決議案はこの求めに応えるための一案である」と述べた。
















