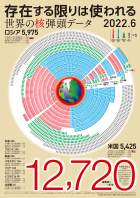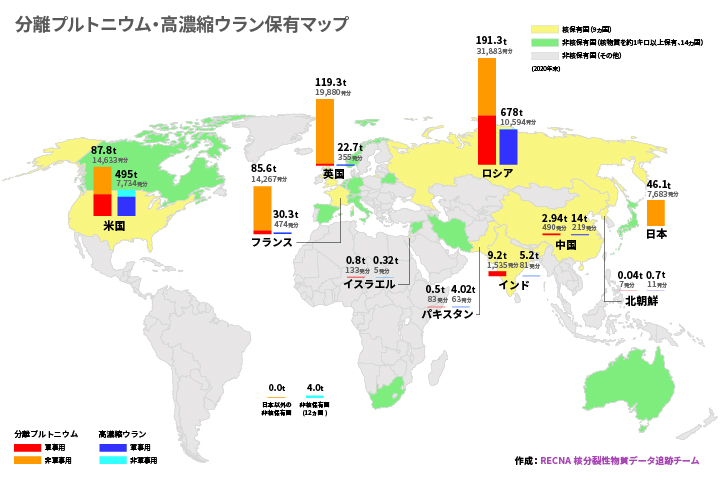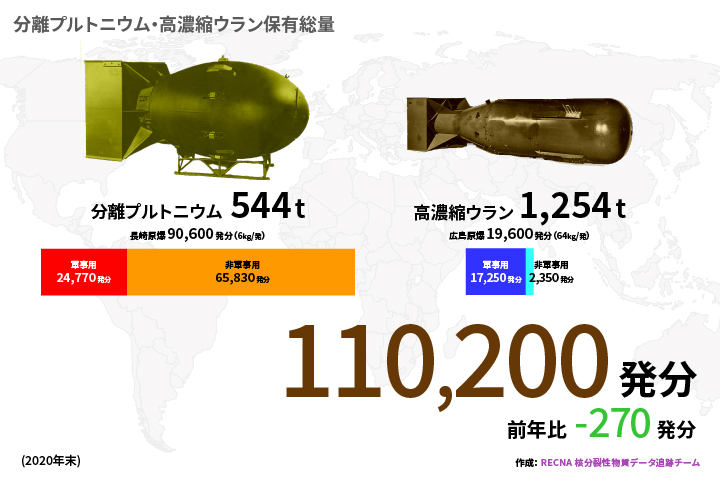ドイツ外務大臣の長崎訪問を歓迎する
長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)見解
2022年7月8日
ドイツのアナレーナ・ベーアボック外相が7月10日に長崎を訪問すると、長崎県及び長崎市が発表した。東京での林芳正外相との会談に先立っての訪問である。長崎原爆資料館の見学、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館での献花の他、被爆者との懇談も予定されている。ウクライナ危機により核兵器使用の懸念が高まる中、その非人道性に目を向けることはますます重要となっている。被爆地のアカデミアとして、この訪問に心から歓迎の意を表したい。
ドイツは、6月21~23日にウィーンで開催された核兵器禁止条約(TPNW)第1回締約国会議にオブザーバー国として出席した。オランダ、ノルウェー、ベルギーとともに、「核同盟」を自認する北大西洋条約機構(NATO)加盟国の中でオブザーバー参加を果たした数少ない国の一つである。
締約国会議で発したステートメントにおいて、ドイツ政府代表は「人道の観点」の重要性を述べるとともに、「建設的な対話に関与し、実際的な協力に向けた機会を模索していく」ことを約束した1。さらに、TPNW第6条、第7条の「被害者援助及び環境修復」問題について「より広範な関心と関与を得るべき」と強調した。締約国会議で合意された「ウィーン行動計画」がTPNW非締約国との対話と協力の拡大を謳う中で、ドイツの前向きな姿勢は今後の新たな展開に希望を与えるものである。核保有国及び日本を含む他の「核の傘」の下にある国々を、「建設的対話」へ引き寄せるリーダーになってほしい。
ドイツは、日本とともに「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)」及び「ストックホルム・イニシアティブ」の中心国として、8月1~26日に行われる核不拡散条約(NPT)再検討会議の成否を左右する重要な役割を担っている。核軍縮の前進に向けたドイツのさらなる構想や行動に期待したい。来年には日本がG7議長国となり、サミットが広島で開催される。今年の議長国であるドイツには、広島サミットで「核なき世界」の実現に向けた強い意志を示せるように、日本と連携を強化してもらいたい。その一環で、G7外相会合を長崎で開催し、核兵器の非人道性に対する認識を一層広げていくための機会とすることを要請する。
1 https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/06/Germany.pdf