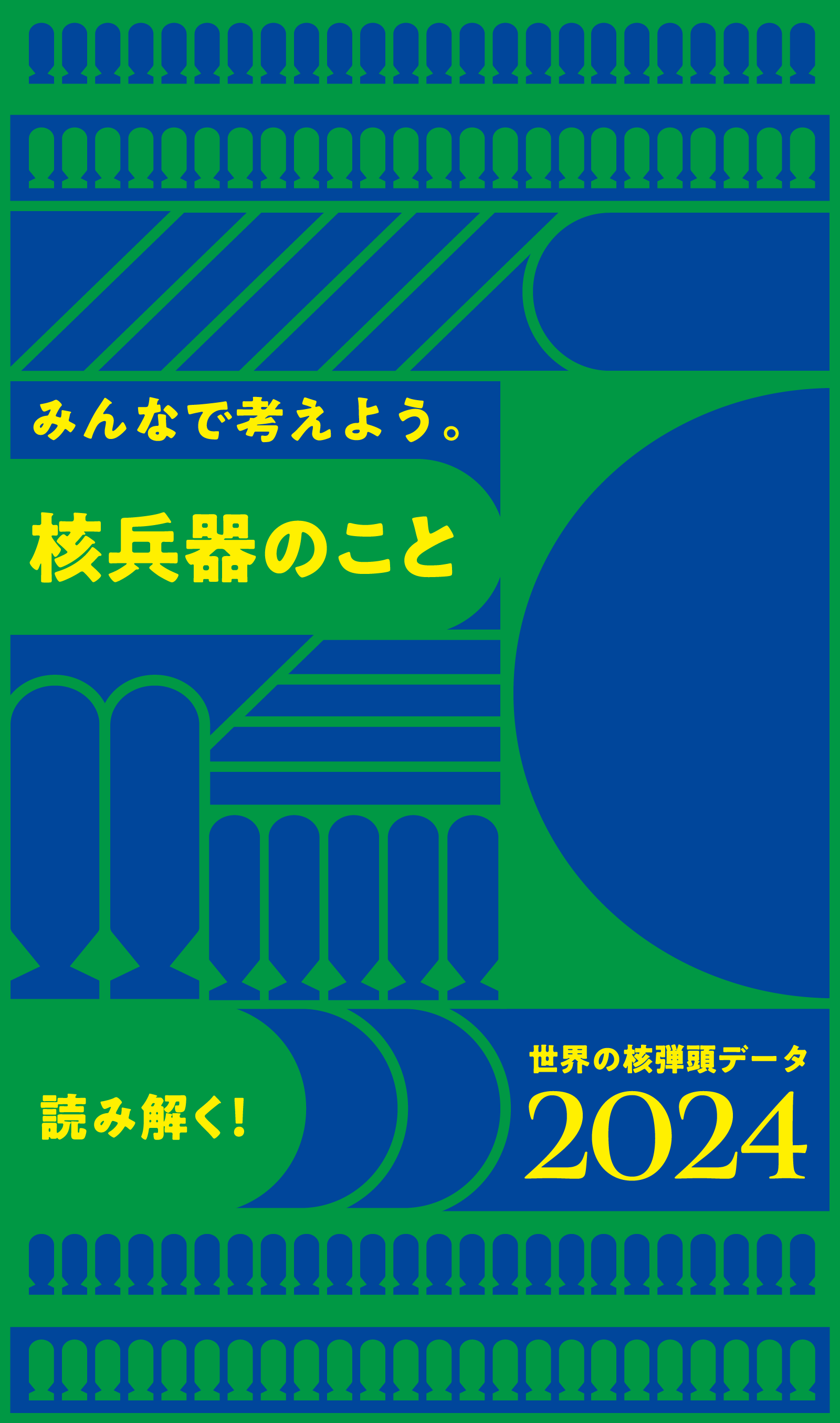このデジタル解説は、「世界の核弾頭データ」ポスターや解説リーフレットを手にとった皆さんが核兵器問題への理解をより深められるように、「よくある質問」をQ&A形式で紹介しています。とりわけ、学校などの教育現場で活用してもらうことを願って作られました。
「世界の核弾頭データ」ポスターは、長崎県、長崎市、長崎大学の三者による核兵器廃絶のための協議会である核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)と、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)が、「核兵器のある世界」の現状をわかりやすく示そうと、2013年に製作を始めました。8月の広島・長崎の原爆忌に向けた平和教育に役立てられるように、毎年6月に最新情報に更新して発表しています。2024年にはポスターのデザインを大幅にリニューアルしました。
ポスターのもととなった詳細なデータベースは、RECNAのホームページで公開しています。さらに詳しい内容を知りたい方はぜひそちらをご覧ください。

ロシア、米国、中国、フランス、英国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の9カ国です。2024年6月現在、これら9カ国が保有するとみられる
核兵器の核爆発を起こす部分。核弾頭と、それを搭載するミサイルなどを組み合わせたものを「核兵器」と呼ぶ。
核弾頭はその置かれた状態によって下記の3種類に分けることができます。この3種類の弾頭をすべて合わせた数が「総数」です。

他方、「現役核弾頭数」は、「総数」から「退役・解体待ち弾頭数」を除いた数です。これは「実際に使うことができる」弾頭の数であり、この動向をみることで、核兵器をめぐって世界がどのような方向に進んでいるかをより正確にとらえることが可能となります。

核弾頭の「総数」でいえば、冷戦後一貫して減少傾向にあります。ピーク時(1987年)に7万発近くが存在していた核弾頭は、米ロが条約を結んで削減するなどして、大幅にその数を減らしました。ポスターが初めて登場した2013年から現在までをみても、「総数」は17,300発から12,120発へと、5180発(およそ30%)減少しています。

ですが、この期間の「現役核弾頭数」の推移をみると、2013年の10,200発から2024年の9,538発へと、削減数はわずか617発に留まります。さらに2018年を起点として、緩やかな増加傾向にあることがわかります。

増加傾向に転じた一つの要因は、米ロ間の新戦略兵器削減条約(
2011年2月に発効した米ロ間の軍備管理・軍縮条約。米ロが配備済み戦略核弾頭数をそれぞれ1,550発以下に削減することなどを定めている。2018年2月の履行期限までに両国ともに目標をクリアした。条約は2026年2月に期限切れを迎えるが、後に続く条約を締結する見通しは立っていない。
先ほど説明したように、「総数」では減っても、「現役核弾頭数」に注目すれば、実質的には「核軍拡」が進んでいるといえます。しかし問題は「数」だけではありません。米ロを筆頭とする核保有国は、古くなった核兵器の最新鋭のものに更新していこうと、莫大な予算を投じて
老朽化が進む冷戦時代の核兵器システムの維持管理のために、旧式の部品の変更、更新などを行うこと。実質的な能力向上となる。近代化は核弾頭だけでなく、ミサイル、爆撃機、潜水艦、核実験施設など多方面にわたる。
ポスターは、2018年から2024年の6年間で、各国の現役核弾頭数の増減率を示しています。増加率が最も高い国から、北朝鮮(233%)、中国(108%)、インド(36%)、パキスタン(21%)と続きます。ロシアと米国の増減率はこれらと比べて低いですが、そもそもこの両国が全体の約8割を占める圧倒的な量の核弾頭を保有していることを忘れてはなりません。
米国は9カ国の中で唯一、数を減らしていますが、先ほど述べたような「質」の面での核軍拡を着々と進めています。どの国も核兵器を手放す気はなく、これから先何十年も核兵器を持ち続けるために動いているのです。

ポスターが示している保有数はすべて推定です。一般的に、核兵器に関する情報は国家の軍事機密であり、いずれの国も詳細なデータを公表していません。とりわけロシア、中国、インド、パキスタン、北朝鮮に関しては、核弾頭の総数を含めて公的な情報はきわめて限定的です。イスラエルに至っては核保有の有無も明らかにしていません。
そこで、この問題に取り組む研究者や専門家は、核兵器の材料となる核物質の保有量など様々な角度からの情報を基に、各国の保有核兵器の数や種類、配備状態を推察しています。ポスターもそうした様々な情報源からのデータを精査して作られています。
いずれの核保有国も、核兵器を持つことが自分の国や仲間の国の安全を守るために必要だと考えています。核兵器による脅しを続けている国がある状況では、自分も核兵器を持ち、いつでもそれを使って相手に壊滅的な被害を与えることができるという姿勢を見せることで、相手に攻撃を思い留まらせることができる――こうした考え方を「核抑止」と言います。核保有国は、安全のための最善策がこうした核抑止力の強化だと考えているのです。また、核兵器を持つことは国家の力を示すことであり、外交交渉において有利になるとの考えもあります。
核兵器は自国の安全にとって不可欠だ、と考えているのは核保有国だけではありません。保有国の
正式には「拡大核抑止」という。核保有国と同盟を組んでいる非核保有国に対して攻撃がされた場合、同盟国である核保有国が核兵器で報復するという姿勢を見せることで、その非核保有国への攻撃を思い留まらせる、という考え方。米国の「核の傘」の下の国として、日本、韓国、オーストラリア、北大西洋条約機構(NATO)の非核保有国。ロシアの「核の傘」の下の国としてベラルーシが挙げられる。
科学技術の進歩により、79年前と現在では核兵器の能力は大きく異なります。現在の核兵器の爆発力は、平均して広島・長崎原爆の数倍から数十倍にも上ります。つまり今の基準で言えば、広島・長崎に使われたは「小型」と言えるのです。
また、核兵器の種類もさまざまに増えています。陸海空のすべてにわたって、長距離を高速で飛ぶもの、ピンポイントで目標を狙うものなど、最新鋭の能力を備えた核兵器の開発・配備が進んでいます。
原爆(原子爆弾)は核兵器の一種。ウランやプルトニウムの原子核が分裂するときに生じるエネルギーを利用した兵器。他に、水素の原子核が融合するときに生じるさらに強力なエネルギーを利用した水素爆弾(水爆)がある。広島に落とされたリトルボーイには高濃縮ウランが、長崎に落とされたファットマンにはプルトニウムが使用された。近代的な核弾頭には高濃縮ウランとプルトニウムの両方が使われている。
広島・長崎の原爆の記憶は、たった一発の核兵器でも使われてしまったら何が起きるか、どれほどの長期にわたって人々を苦しめ続けるのかを示しています。
加えて、近年においては、いくつかの研究機関が、核兵器使用の様々なケースにおける被害想定を発表しています。たとえば米プリンストン大学が現実的な核戦争計画を基に作ったシミュレーション動画「PLAN A」は、米国ら西側諸国とロシアの対立が核全面戦争にエスカレートし、紛争発生からわずか数時間で9千万人以上の死傷者数が出ると予想しています。
核戦争が世界規模の気候変動を生むとの研究結果もあります。米ラトガース大学などの論文によれば、米ロ間で全面核戦争が起こった場合、大気中に放出されたすすや塵がもたらす気温低下により農作物が壊滅的な被害を受け、地球規模の飢饉が生じて50億人あまりが命を落とすと報告されています。
またRECNAなどが発表した北東アジア地域における核兵器使用の被害想定では、攻撃を受けた地域で数か月以内の死者は数百万人、さらに放射線の影響などで1年以上経過した後の死者も数十万人に上る場合があるとしています。
核兵器はいわば精密機械です。まずは兵器として使用することができないように、核兵器を解体して処分します。核兵器の製造と同様、核兵器の設計情報や材料となる核物質が外部にもれないように、きわめて慎重な作業が求められます。
しかし解体して終わり、ではありません。問題は核物質です。核物質は簡単になくなりません。したがって、取りだした物質が二度と核兵器に利用されないよう、原子力発電の燃料に転換したり(高濃縮ウラン)、核のゴミとして地下深くに処分したり(プルトニウム)することが必要です。これは、決してたやすいことではなく、国際的な監視も必要です。しかし残念ながら世界の核物質量は現在でも増え続けているのです。
一発を作るための費用を計算することは容易ではありません。その国がすでに多くの核兵器を保有しているのか、それとも開発をゼロから始めるのかでかかる費用は大きく異なるからです。その国がすでに持っている技術力にも左右されるでしょう。また、核弾頭そのものにも、さまざまな種類や性能のものがあり、一括りにすることは困難です。
参考までに、米国の原爆開発計画「マンハッタン計画」では、1942年から45年までの間に、当時のレートでおよそ20億ドル(1ドル150円で3000億円。以下同じ)にも上る巨額が投入されました。現在の貨幣価値に換算すると300億ドル(約4兆5000億円)を優に超える額になります。
核兵器を使用させないためには、各国間の対話を促し、二国間・多国間の軍備管理・軍縮体制の立て直しを図り、核軍拡競争がこれ以上進んでいくのを止めていかなければなりません。
2018年2月の新START履行期限を境に、「現役核弾頭」が増加傾向に転じていることは、新STARTの後継となる新たな軍備管理・軍縮の枠組み作りを急がなければならないことを示しています。また、今後の米ロ交渉においては、核弾頭や運搬手段の削減だけでなく、新型核兵器の開発など「質的」な軍縮についても議論に含められるべきです。
こうした目の前の危険を回避する策を講じると同時に、私たちが忘れてはならないのは、「核兵器を二度と使わせないための唯一の保証は、核兵器廃絶である」という点でしょう。核兵器が存在する限り、事故の可能性を含め、使われる危険性は残ります。そして一旦核兵器が使われてしまったら、それは全人類の滅亡に繋がる核戦争へと拡大しうるのです。
核兵器のない世界を実現するためには、核保有国だけでなく、すべての国の力が必要です。国際的な核軍縮と不拡散の要石である核不拡散条約(NPT)は、その第6条で、すべての国に核兵器廃絶に向けた誠実な軍縮交渉を義務付けています。とりわけ、日本など、核保有国の「核の傘」に依存している国が政策を転換し、「核兵器に頼らない安全保障」をめざしていくことが重要になります。北東アジア非核兵器地帯の創設に向かうことはそうした努力の一つです。
もっと詳しい提言については、RECNAのホームページをご覧ください。